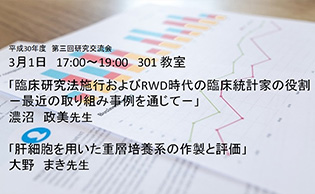ドイツのロッテンブルクで薬局(セントラルアポテーケ)を開設している薬剤師のアッセンハイマー慶子氏に、「薬剤師のミッション~インポッシブルからポッシブルへ」と題したご講演をいただきました。
| 日時 | 演題 | |
|---|---|---|
| 7月13日(金) | ドイツ ロッテンブルク 薬局(セントラルアポテーケ)開設者 アッセンハイマー慶子氏 |
薬剤師のミッション~インポッシブルからポッシブルへ |
薬剤師の使命について、「国民の健康維持に貢献し、安定な医薬品供給により人の命を救うこと」という立場から、医薬品なくして医療は成り立たないことを前提にすると、薬学が全ての命に関わるオールラウンドの学問であることを明言されています。その上で、薬学の知識で、薬剤師は地域と連携し、様々な活動ができることを具体的な例を通して説明され、学生時代に学ぶ基礎教育の重要性を熱く語られました。さらにご自身の深い経験に基づいた、日独薬事事情の比較により、薬剤師の使命を全うできる薬局環境について多くのご提言をいただきました。
参加した学生や教員からは、ドイツと日本の薬学教育、薬局業務等の違いなど、薬局環境と社会との関わりについて多方面から多くの質問が寄せられ、機会があれば再演を希望する声も上がり、予定された質疑応答の時間を超える内容となりました。

薬学部 薬学科 小松 俊哉 教授と同学科 建部 卓也 助教が下記演題で講演を行いました。
| 日時 | 演題 | |
|---|---|---|
| 11月30日(金) | 小松 俊哉 教授 | 薬理活性化合物の合成と新規反応の開発 ‐これまで、そしてこれから‐ |
| 建部 卓也 助教 | アルツハイマー病におけるグリア細胞の可能性について | |
小松 俊哉 教授 「薬理活性化合物の合成と新規反応の開発 ‐これまで、そしてこれから‐」
複雑な化学構造を有し、顕著な薬理活性を有する海洋産天然有機化合物Preswinholide Aの全合成研究と、そこから着想を得て現在研究を進めている二方向型ニトロアルドール反応の開発に関する話題を中心に講演を行いました。

建部 卓也 助教「アルツハイマー病におけるグリア細胞の可能性について」
アルツハイマー病は、進行性の認知機能障害を特徴とする神経変性疾患で、治療法・予防法の確立が急務となっています。本交流会ではアストロサイト由来のAβ分解酵素KLK7を発見したため、その経緯と今後の展望について講演しました。

薬学部 薬学科 濃沼 政美 教授と同学科 大野 まき 講師が下記演題で講演を行いました。
| 日時 | 演題 | |
|---|---|---|
| 3月1日(金) | 濃沼 政美 教授 | 臨床研究法施行およびRWD時代の臨床統計家の役割 ‐最近の取り組み事例を通じて‐ |
| 大野 まき 講師 | 肝細胞を用いた重層培養系の作製と評価 | |
濃沼 政美 教授「臨床研究法施行およびRWD時代の臨床統計家の役割-最近の取り組み事例を通じて-」
2018年度に臨床研究法および次世代医療基盤法が施行され、我が国の臨床研究を取り巻く環境は大きく変化しました。
そのような中、臨床統計家の役割はどのようなものであるのか。厚労科研・AMEDなどの補助金を用いて実施した研究を中心に、最近の事例を紹介します。
大野 まき 講師「肝細胞を用いた重層培養系の作製と評価」
創薬研究においてヒト肝細胞を用いた薬物動態評価は必須ですが、通常の細胞培養では薬物代謝機能は急速に低下します。ヒト肝細胞と内皮細胞の重層培養では、肝細胞機能上昇と細胞外環境の変化がみられました。その詳細について講演を行いました。